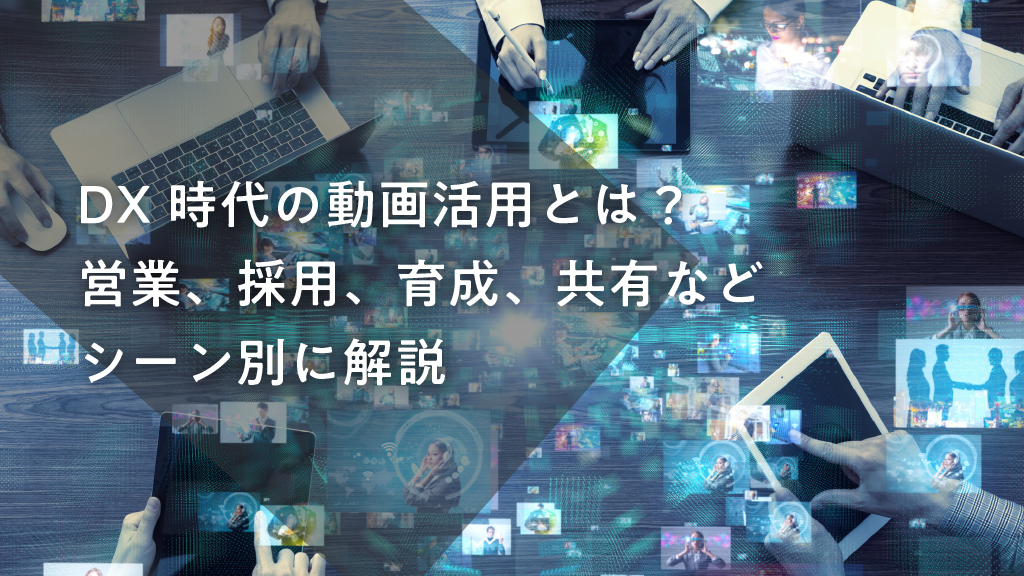スマホやIoT家電など、プライベートとビジネスの両方でデジタルツールの活用が欠かせない現代において、新たなビジネスの概念として注目されているのがDXです。
DX推進のために多くの企業は「社会全体のデジタル化の促進」「消費者やユーザーの行動変化」「ITシステムの老朽化」への対応が考えられ、多様化するビジネスやデジタルサービスのツールの選定や従業員への浸透など、さまざまな課題がありますが、解決策のひとつとして動画活用があげられます。
身近な変化で言えば、「Uber eats」のようにこれまで電話等で出前を配達していたものが、アプリ上で各店舗が営業状況に応じて配達の有無やアプリを通して個人の配達員をピックアップして、消費者に届けられるという画期的な変化が上げられます。
そういった状況の変化でも、「Wolt」「menu」「出前館」といった同じようにアプリで配達ができるデリバリーサービスも普及しており、それぞれの特徴として「配送エリア」「取扱い店舗」「配送時間」「商品価格や送料」といった競争性があり、社会や人々の生活をより良いものに変化させているのもDX推進の一つの事例と言えるでしょう。
本記事では、DX推進が叫ばれる中で期待できる、動画活用の有用性について解説します。
目次
そもそもDXとは?
DXとはデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)のことです。特定の施策ではなく、進化したIT技術の浸透によって、生活をより良いものに変化させる概念をさします。
DXの定義としては以下の3つがあります。
1)デジタルトランスフォーメーション
2004年に海外でスウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルターマンらが発表した論文『 Information Technology and The Good Life 』の中で提唱されたのが起源だと言われています。
論文ではDXを「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義し、情報技術が物理世界のあらゆるものと結びついて変化を起こしつつあることを指摘しています。
引用:Information Technology and The Good Life
2)デジタル「ビジネス」トランスフォーメーション
スイスのビジネススクールであるIMDのマイケル・ウェイド氏らによって、2010年代に提唱された概念です。デジタル・ビジネス・トランスフォーメーションでは、「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」と定義しています。
エリック・ストルターマン氏が提唱しているデジタルトランスフォーメーションと区別するために、デジタル「ビジネス」トランスフォーメーションといいます。
IMDが毎年公表する「世界デジタル競争力ランキング2021」によると、日本のデジタル競争力の総合順位は「28位/64カ国・地域」とされています。世界と比べて、日本のデジタル競争力は低下傾向の要因の大きな1つが「人材領域が47位」「デジタル・技術スキル領域が62位」と「人材面での競争力の低さ」と言われています。世界から見た日本の社会としてDXを推進することが求められていると考えられます。
3)経済産業省が公表した定義
一方、日本国内では上記の世界的な流れに追従して、2018年に経済産業省が「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義づけています。
「経済産業省内や自治体のDXを推進する活動・計画」の公式サイトによると、
文書や手続きを単に電子化するだけではなく、
ITを徹底的に活用することで、手続きを簡単・便利にし
蓄積されたデータを政策立案に役立て、
国民と行政、双方の生産性を抜本的に向上する
ことを目指します。とされています。
引用:経済産業省内のデジタルトランスフォーメーションとは(2020年6月)
DXを進める3ステップ
世界中でDXへの注目が集まる一方で、国内企業のDX推進は滞っているのが現実です。現状を打破して本格的にDXを進めるためには、以下の3ステップを理解したうえで、時には並行して取り組む必要があります。
ステップ1:デジタイゼーション
まずデジタイゼーションで書類や名刺など、アナログデータのデジタルデータ化を行います。紙の書類や名刺をアナログのまま使用していると、保管場所や紛失リスクの問題だけではなく、リモートワークの導入に支障が出たりデータが属人化して効果的に活用できなかったりと、次のステップのデジタライゼーションにも影響を及ぼしかねません。
ステップ2:デジタライゼーション
デジタライゼーションは、デジタル化したデータを使用するなど、個別の業務や製造プロセスにデジタル技術を浸透させることです。たとえば従来は紙の書類で行っていた情報共有を、メールやチャット、ファイル共有サービスを利用した方法に変革することもデジタライゼーションにあたります。
ステップ3:デジタルトランスフォーメーション
最後のステップ、デジタルトランスフォーメーションは、デジタイゼーションとデジタライゼーションの両方が実行済みであることを前提としたものです。業務や製造のデジタル化によって、これまでになかった新たな事業で顧客起点の価値を創出したり、ビジネスモデルに変革をもたらしたりすることを目指します。「動画の活用」は、このステップ3の「紙媒体の動画マニュアル化」「顧客とのコミュニケーション方法の効率化」などを例とした一つの手段として、デジタルトランスフォーメーションに該当します。
DX推進における動画活用の有用性
DX推進は、単純にデータをデジタル化するなどIT機器やサービスを導入することがゴールではありません。デジタル化はあくまで手段であり、目的は業務・製造フローの変革ひいては新たな価値やビジネスモデルの創出です。
新たな価値やビジネスモデルにつながるデジタル技術の活用方法として、たとえば動画があげられます。近年は動画投稿サイトの浸透やスマホの普及、5G技術到来により、企業においてもプロモーションなどさまざまな用途で動画が活用されています。
動画は映像、音声、テロップが互いの不足した情報を補い合い、一度に膨大な内容を伝えることができるのが大きなメリットです。動画活用することによって、短時間で情報量の充実さや幅広い表現でコミュニケーションを取ることができ、非対面でも効果的な顧客アプローチを可能とするなど、いまや企業のDX推進になくてはならない手法のひとつといえます。
「Video BRAIN」などのクラウド上でどこでも動画制作や編集ができるツールを利用することによって、PC端末に動画編集ソフトや動画制作会社へ依頼しなくても社内で簡単に動画制作ができるような時代になってきています。
シーン別、DXを推進する動画活用
広告の一種としても活用されるほど、あらゆる動画コンテンツが社会に浸透しているのが現在です。また、プロモーションやエンターテイメントとしての役割だけではなく、動画活用は新たな技術や知識の取り込みにともない、企業のDXを推進する手法としても期待できます。
ここではDXを推進する動画活用について、「営業シーン」「採用シーン」「育成、共有シーン」の3パターンに分けて紹介します。
1)営業シーンでの動画活用
営業活動では、売上につなげるために商品・サービスのメリットや価格に見合った価値を伝えなくてはなりません。紙の資料でも伝わる部分はありますが、商品・サービスによっては具体的な使用イメージがわかず、他社と比較されたり失注につながることがあります。
たとえば組み立て式の家具を販売したいとき、文字や画像で「組み立てやすい」と説明するよりも、実際に組み立てている動画を視聴してもらうほうが商品のメリットを実感してもらえるでしょう。
このように商談で動画を取り入れると、実際に使用している様子を動画で確認できるため、ユーザーも使用イメージが浮かびやすくなります。テレビの通販番組などでも、出演者が使用するシーンや購入者のインタビュー映像を盛り込むことで、視聴者に購入後の自分をイメージさせ注文につなげています。
動画の構成内容を工夫すれば、ユーザー自身が気付いていなかった潜在的な課題や需要を認知させ、検討から公式サイトへのアクセスや資料請求など具体的な行動を促すこともできるでしょう。
2)採用シーンでの動画活用
採用活動で課題となりやすいのが、自社が求める人物像とは異なる人材からの応募が多くなることや、採用後のギャップによる早期離職です。欲しい人材以外からの応募が多ければ選考に時間がかかり、理想の人材に割ける時間が圧迫されます。早期離職が多ければ再度募集をかけることとなり、求人にかけるコストが膨れ上がってしまうため、予算の観点からしても避けたい問題です。
このようなトラブルを防ぐ方法のひとつが、動画活用です。実際に働いている先輩社員のインタビューや職場の様子、経営理念などの企業文化を動画で発信することにより、自社のカラーに合った人材が応募してくれるうえ、ギャップによる早期離職のリスクも軽減されます。
また、オウンドメディアやリクルートサイトなどにも動画を表示すると、自社の認知度向上も期待できるでしょう。
3)人材育成、共有シーンでの動画活用
従業員の育成や情報共有シーンにおいても、動画が活用されています。たとえば従来のマニュアルはPDFなど紙媒体のものが多く、伝える手段がテキストや画像に限られていましたが、動画でマニュアルを制作すると、実際の動きを伝えることができます。
テキストや画像では分からない、こまかな部分を含めた作業手順を映像で伝えながら、音声で補足説明を行えるため、紙媒体よりも多くの情報を伝えられるのが大きなメリットです。また、現場で作業を進めながら伝える場合と異なり、動画であれば分からない部分を繰り返し再生して学ぶこともできます。
複雑な作業手順が動画なら容易に理解できるため、社内のデジタライゼーション(業務・製造プロセスでデジタル技術を浸透させること)にも大いに役立ちます。
4)お客様とのコミュニケーションや満足度(エンゲージメント)の向上
製品メーカーや小売販売している事業者にとって、実際に購入したユーザーとのコミュニケーションをする機会が殆どないため、「広報活動」「ブランド商品ページへの掲載」「SNSでの配信」「直販サイトへの掲載」といった様々な手段で直接ユーザーとのコミュニケーションを取る手段として有効です。
流通経路の中で不足している静止画のみや、クレームに繋がる可能性のある取り扱い方法をマニュアル動画にするなどもITやDX活用の一例として、購入しているユーザーのコミュニケーション方法として利用するとよいでしょう。
動画を活用したDX推進事例
1.株式会社オールハーツ・カンパニー
全国にベーカリーとパティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー社は、2002年の創業当初から根強い人気を誇る「マジカルチョコリング」、高級食パンにかわいらしさをプラスした「ねこねこ食パン」など数々のヒット商品を生み出しており、「各店舗のサイネージに期間限定の商品紹介や各店舗の調理品質を上げるためのレシピマニュアル」などに動画を利用しています。
2.イズミテクノ株式会社の事例
アルミニウムの金属パーツに「アルマイト」という表面処理を施す株式会社イズミテクノ。事業拡大に伴う教育体制の見直しに伴い、紙ベースでアップデートされず活用しきれていなかった「50種類以上の1マニュアルあたり数十ページある作業手順書の動画の量産化」を「Video BRAIN」で動画制作を行っています。
3.株式会社湖池屋
「ポテトチップス、コイケヤプライドポテト、カラムーチョ、スコーン、ポリンキー」などのロングセラー商品を発売している総合スナックメーカーの小池屋。 商品の商談資料から店頭でのサイネージ、社内マニュアルまでパワポ感覚でクオリティの高い動画制作ができることにメリットを感じ「Video BRAIN」を導入し、「セールスからの問い合わせが50%UP」を実現しています。
4.株式会社アイジーコンサルティング社の事例
新築設計・施工、不動産仲介及び売買、総合リフォーム事業、耐震補強事業、住宅メンテナンス事業など、総合的な住環境づくりを行う、株式会社アイジーコンサルティング。不動産業界の中でもいち早くDX化を推進し全社タブレット支給や営業マニュアルの動画化に取り組む。「新卒の契約数が4倍」「1本あたりの制作コスト削減と編集の充実」「継続的なサポートの手厚さ」で「Video BRAIN」で営業マンやお客様向けのマニュアル動画を制作。
5.INEST株式会社
INEST株式会社は「セールスに付加価値を」をミッションとする営業支援を行う企業です。マーケティングとセールスのノウハウを駆使し、幅広い営業支援サービスを提供している同社では、「人事・採用向けに会社の雰囲気の理解」「内定承諾率UP」「対外向けの広報」にVideo BRAINで制作した動画を活用しています。
6.ティーペック株式会社
ティーペック株式会社は「日本の新しい健康インフラになる」ことを経営ビジョンに掲げ、ヘルスリテラシー向上のために「日常の座り過ぎやテレビの見過ぎによる寿命低下などの健康への気づきを与える」ための社内向けマイクロラーニングや外部研修向けに「Video BRAIN」で制作した動画を活用しています。
まずは無理のないところからDX推進やコミュニケーション手段の改善の手段として動画活用を進めてみるのはどうでしょうか
DX推進は世界的に注目された概念であり、国内企業も積極的に取り組むべき課題のひとつです。一方で書類をデータ化するなどのデジタイゼーションや、デジタル技術を業務フローに浸透させるデジタライゼーションの段階で中断しつつある企業も多いのではないでしょうか。
身近な取引先や購入してもらっているユーザーとのコミュニケーションや継続的にサービスを提供する上での課題から洗い出すだけでも、検討するきっかけになると思います。
社内のDX推進が滞っている場合は、無理のない範囲から始めることをおすすめします。たとえばマニュアル制作や採用活動などで動画を活用すると、伝えたい情報がより伝わりやすくなり、従業員や求職者にも浸透しやすいでしょう。デジタルツールの操作方法も動画なら容易に説明できるため、他の業務や製造フローにおけるDX推進にも発展させられます。
動画制作の内製化を検討しているなら、動画自動生成ソフト市場シェアNo1の動画制作・編集ツール「VideoBRAIN」もご検討ください。素材とテンプレートを入れるだけで未経験の方でも今すぐ動画制作を始められます。
この記事をシェアする