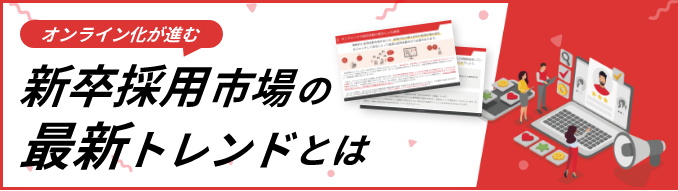採用において「歩留まり」に悩む担当者は多いのではないでしょうか。「内定を出しても辞退する人が多い」「エントリー数は多かったのに、説明会には全然人が集まらない」など、採用活動の課題解決に役立つのが「歩留まり」です。
この記事では、採用において歩留まりが重要な理由をふまえ、歩留まり率を上げるためのポイントを解説していきます。
目次
採用における「歩留まり」とは
そもそも「歩留まり」とは、製造業など生産全般において、原料や素材の投入量に対し、得られた生産数量の割合を指します。その出来高の割合をパーセントで示したものが「歩留まり率」となります。
採用活動において言い換えると、採用における各選考に進んだ人数の割合を指します。
歩留まり率の計算式
歩留まり率は「選考通過数」÷「選考対象数」×100で計算できます。
<例:新入社員数が5名で、内定者数が10名だった場合>
「実際に入社した人数(5名)」÷「内定を出した人数(10名)」×100=歩留まり率は50%となります。
採用の歩留まり項目
企業によって様々ですが、採用活動は、主に以下の流れで選考が進んでいきます。各フローが採用の歩留まり項目となります。
・エントリー
・説明会
・書類選考
・筆記試験
・一次面接
・二次面接
・最終面接
・内定出し
・内定承諾
・入社
各項目ごとに歩留まり率を計算するようにしましょう。数値から、自社の課題がわかるようになります。
<例:エントリー数が100名で、次の説明会参加に進んだ人数が50名だった場合>
「実際の説明会参加者数(50名)」÷「エントリー数(10名)」×100=歩留まり率は50%となります。
なぜ歩留まりが重要なのか
採用活動の場合、歩留まり率が高いほど次のフェーズへの通過者が多くなります。一方、歩留まり率が低ければ脱落者が多いといえます。
たとえば、自社のエントリー数が100名だったのに対し、開催した説明会に参加したのが50名だったとします。つまり、エントリーしたものの、説明会という次のフェーズに移行するのをやめた人が半数です。
その場合「説明会の内容が弱い」「日程の選定が適切ではない」など、さまざまな要因が考えられます。歩留まり率を見て、どの項目に自社の採用課題があるのかわかるようになります。
つまり、採用活動を見直す際に歩留まり率がポイントになります。
採用担当者が抱える主な悩み
ここから、採用担当者が抱えている課題を解説します。自社の採用活動の状況を思い浮かべながら、確認していきましょう。
新入社員の数を確保できない
1つ目は、新入社員の数を確保できないという課題が挙げられます。現在、新卒採用は売り手市場が続いており、企業側は学生を確保するのに苦戦しています。
ただし、その原因はいくつか考えられます。そもそもエントリー数が集まっていないこともあれば、内定数に対して実際に入社する社員数が少ない場合もあります。各フェーズの歩留まり率を分析し、原因を洗い出す必要があるでしょう。
さまざまな採用業務がある
ひとくちに採用活動といっても、さまざまな業務があります。採用サイトの開設から候補者とのやり取りや調整、選考、内定後の研修や懇親会の実施など、担当者は多くの仕事を行います。
担当者が多忙になってくると、採用活動の課題を洗い出す作業や分析などの時間を割くのが難しくなってきます。その結果、前年の課題に対する解決策を打てないまま、採用活動を進めていかなければなりません。
採用コストを抑えられない
採用活動にかけられるコストには限度があります。そのため、「あまりコストはかけたくないけど、応募者が減ることは避けたい」と悩んでいる採用担当者は多いのではないでしょうか。
この課題を解決するポイントは、できるだけ小さいコストで済む方法に置き換えられる活動を見つけることです。たとえば、SNSを使ったプロモーション活動や、オンライン面接は従来の採用広告や対面面接よりコストを下げられるでしょう。
採用の歩留まり率が低下してしまう原因
採用活動において、歩留まり率の低下には以下のようなさまざまな原因が考えられます。ここから、歩留まり率が低下してしまう主な原因について詳しく解説していきます。
内定取得数の増加による影響
現在、求職者1人当たりの内定取得数が増加しており、そのことが歩留まり率に影響を与えています。
今の採用市場は売り手市場であり、1人の応募者を数社で取り合っている状況です。そんな中で、自社への入社を決めてもらうのは簡単なことではありません。
求職者によっては、10社以上の企業から内定をもらっているケースもあるため、倍率は単純計算で10倍になります。
情報拡散による影響
2つ目の原因は、情報拡散による影響です。現在は企業に関する情報の量と拡散力が圧倒的に大きくなりました。これは、インターネットとSNSの発展によるところが大きいです。
しかし、良い情報ばかりが蓄積・拡散されているとは限りません。中にはネガティブな情報もあり、内定辞退に影響を与えていることも考えられます。
人は良い情報よりも悪い情報を過大評価する傾向があるため、少ない情報量でも大きな悪影響を生み出してしまう可能性があります。
採用ブランディングの不足
採用ブランディングの不足も、歩留まり率の低下の原因になることがあります。採用ブランディングとは、自社で働くことについて応募者に正しく認知してもらうための活動です。
企業はただ単に良い情報を発信し続けたり、商品のアピールをしたりするだけでは、十分な応募者を集めるのは難しいと言えます。採用の成果を上げたいのであれば、顧客向けのPR活動とは違う、求職者向けのブランディングが必要です。
応募者へのフォロー不足
採用活動に必要なリソース不足など、様々な原因によって、応募者へのフォローが不足してしまうことも、歩止まり率の低下を招きかねません。
たとえば応募者の不安を拭うために、問い合わせのメールや電話に速やかに対応することは、求職者に対するとても大切なフォローです。求職者も入社意欲が高まるでしょう。
しかしフォローが不足してしまえば、求職者が抱く自社へのイメージを低下させることになりかねません。応募者を大切な顧客だと捉えて、丁寧にフォローしていくことを心がけましょう。
応募者と企業のミスマッチ
採用の各段階で、応募者が「イメージと違った」とギャップを感じる場合があります。その際、自社の情報発信やPRの方法に問題がなかったか見直しましょう。
たとえば、過剰なPRを行なってしまうと、会社説明会の際に「ネットに載っていた情報と違う」と思われる可能性があります。
また、採用の各工程に一貫性がないこともミスマッチを引き起こします。これを防ぐためには、採用のコンセプトをしっかりと固めて、発信内容やPRに一貫性を持たせることが大切です。
採用活動で歩留まり率が低下しやすいポイント
選考の流れの中で、歩留まり率が低下しやすいフェーズがあります。
エントリー〜会社説明会
気軽な気持ちでエントリーする方も多いため、「思ったより会社説明会に人が集まらなかった」ということがあります。会社説明会に足を運んでもらうためには、エントリー後すぐに説明会を開催すると効果的です。
エントリー〜書類選考
多くの企業は、書類選考の段階で他のフェーズよりも多くの応募者を落選させます。これは、面接の手間をなるべく減らすためです。
そのため、面接で応募者の人数が減ってしまうのは、ある程度仕方のないことだと言えるでしょう。
書類選考通過〜面接
面接は応募者にとって、手間や心理的なコストが最も大きいフェーズです。そのため、気軽な気持ちで応募してきた人の多くは、面接のタイミングで姿を消してしまいます。
採用の歩留まり率を改善するための対策方法
コストを上げたり、施策を大きく変えたりする前に、現在のやり方を改善するだけで効果があるかもしれません。例えば、以下のような対策が考えられます。
採用フローの期間を短縮する
採用フローの期間を短くすることを検討しましょう。多くの応募者は複数の内定を抱えているため、採用フローが長期化すると、内定者を競合他社に取られてしまう可能性が高くなります。
目標の採用期間は、2週間~1ヶ月以内。応募者の興味が他の企業に向く前に結果を出すことが大切です。
各歩留まり項目間の期間を削るだけでも、大きく採用期間を短縮できます。一度、現在の採用フローを見直してはいかがでしょうか。
採用広報をする
企業の魅力や強みは、十分に応募者に伝わっているでしょうか。応募者に自社のことを深く知ってもらうためには、質の高い採用PRが欠かせません。
採用PRがうまくできていないと、欲しい人材がどんどん競合他社に流れていってしまいます。
特に、複数の企業から内定をもらっている応募者は、一番やりがいや魅力を感じる企業へ入社を決めるケースが多いでしょう。最後の最後で人材を逃さないためにも、採用PRのブラッシュアップはとても大切です。
内定者とこまめにコミュニケーションを取る
内定者と積極的なコミュニケーションを取ることで信頼関係を築くことも、歩留まりを改善するためにおすすめできる方法です。
選考フロー以外のタイミングでも内定者との接点を持ち続けることで、企業に対する良い印象を形成できます。
たとえば、チャットツールで相談に乗ったり、内定者を集めて懇親会を開いたりしてみましょう。内定者の心配や不安を取り除くことがポイントです。
歩留まりの改善に役立つツールやサービス
現在は、採用活動に役立つさまざまなツールやサービスが存在します。導入する場合、自社の状況に応じて取り入れるのがおすすめです。ここでは、主な課題ごとに役立つツールやサービスを紹介します。
採用のノウハウ不足なら:採用代行サービス
社内に採用のノウハウが不足していたり、採用活動に詳しい経験者がいなければ、採用代行サービスをおすすめします。
業務の一部を外注することにより、知見が求められる業務を社外の担当者に任せられます。一部業務のみの依頼もできるため、「難易度の高いフェーズだけプロに任せる」といったことも可能です。
「予算はあるが、人的なリソースが足りない」という時は、採用代行サービスを検討してみましょう。
人手不足なら:採用業務の自動化ツール
採用活動の中には、自動化して対応できる業務もあります。たとえば、応募の確認メールや説明会への案内メールなどは、応募者によって内容を変える必要がありません。よって、自動返信機能が搭載されたツールを使って自動化しましょう。
自動化できるタスクをツールに任せることで、担当者は別のタスクに集中できるようになります。
候補者が集まらないなら:オンライン面接ツール
オンライン面接は、候補者を集めるために有効な手段の一つです。オンライン面接の最大のメリットは、遠方に住んでいても参加しやすい点にあります。学生の交通費や心理的ハードルを下げられるため、エントリー数の増加が見込めます。
もちろん、ZoomやTeamsのような通常の会議で使うツールでも、オンライン面接は実施できます。オンライン面接ツールを使うメリットは、採用活動に役立つ機能が搭載している点です。ヒアリングシートや評価シートが記入できたり、採用の進捗を管理できる機能など、必要に応じてチェックしてみると良いでしょう。
スムーズに連絡を取るなら:コミュニケーションツール
電話やメールで連絡を取り合っている企業もありますが、連絡手段を不便に感じている応募者もいます。特に若い世代には、メールや電話のやりとりを煩わしく感じるかもしれません。
現在は、LINEやSlackなどのさまざまなコミュニケーションツールが普及しているため、目的に合わせて利用するツールを使い分けることが大切です。
「やりとりが面倒」という理由だけで内定を辞退されてしまうのはもったいないもの。応募者の特性や世代、職種などに合わせてツールを選ぶようにしましょう。
採用広報を強化するなら:動画編集ツール
自社の情報を見てもらうには、採用広報の強化は欠かせません。中でも、動画で情報を収集する学生が増えているため、動画の発信は欠かせないものとなっています。
採用広報として発信するべき動画の内容は、採用のフェーズや課題によっても異なります。
(1)事業内容の紹介
<動画の内容:自社の技術に関する紹介>
動画の導入では「就活生の1日」として、起床から就寝までのスケジュールを紹介しながら、日常生活の中で同社の技術が活用されているポイントを紹介しています。後半のパートでは、同社が扱う界面活性剤の働きを紹介し、事業内容をわかりやすく解説した流れとなっています。
<期待される効果:学生の認知・理解度の向上>
新卒採用の場合、消費者が目にする商品・サービスなどを扱うtoCメーカーなどに応募が集まりやすい傾向にあります。動画を通して、日本でシェアNo.1を誇る繊維用加工剤メーカーである同社の技術が、知らない中でも身近なところに活かされていることを知ってもらえます。その結果、同社の事業に興味を持ったり、関心が高まったりする効果が期待できます。
(2)社員インタビュー
<動画の内容:対談形式の社員インタビュー>
入社のきっかけや業務内容について、社員にインタビューした内容を動画で紹介しています。対面ではなくオンライン上で行っており、拠点が離れた社員ともスムーズに実施されています。
<期待される効果:学生に向けた自社理解・エンゲージメント向上>
インタビューを通じて、社員の考えや業務内容を知れるとともに、社員同士で話すことにより、会社の雰囲気も伝わりやすくなっています。また、インタビューされる社員においても良い影響が生まれます。自身の業務や会社の魅力を振り返れるため、エンゲージメント向上が期待できます。
(3)内定者に向けたメッセージ
<動画の内容:内定後、内定者に送るメッセージ>
YouTubeなどに一般公開する方法だけでなく、個人宛に動画を送ることも一つです。
たとえば、内定が決まった際に、内定通知とともに動画で本人にメッセージを送る企業があります。選考の担当者や経営陣などからコメントをもらい、内定者の印象や期待していることなど、映像を通して思いを伝えます。
<期待される効果:内定辞退の防止>
電話やメールなどで、企業からメッセージを送るよりも、動画で担当者から話してもらう方が思いも伝わりやすくなります。その結果、入社意欲が高まり、内定辞退の防止につながります。
採用の歩留まりを動画で改善させるなら、Video BRAIN
採用の歩留まりを改善するために動画を取り入れたくとも、「編集するスキルがない」「どのように動画を作れば良いのかわからない」と悩む担当者も少なくないのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、ビジネス動画編集クラウドの「Video BRAIN」です。Video BRAINは、誰でも簡単に動画が制作できるツールです。3,500以上の動画テンプレートが搭載されており、採用動画で使える素材が多数揃っています。
パワーポイントのような感覚で操作できるため、「動画編集は未経験でも、パワポで資料を作る機会がある」という方には使いやすいツールとなっています。
まとめ
採用活動の見直しを行う上で重要になるのが歩留まりです。歩留まり率を算出し、どの過程で課題があるのかをまずは見つけましょう。その上で有効な対策をとり、次の採用活動につなげていくことが重要です。
関連記事
この記事をシェアする